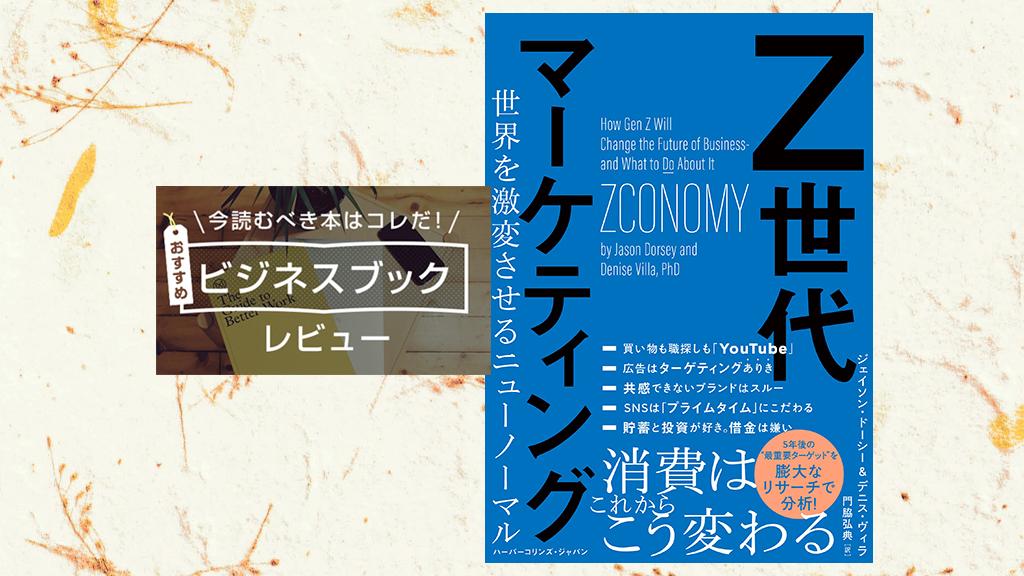『WIRED』日本版前編集長の若林恵が主宰するコンテンツレーベル、黒鳥社による「blkswn jukebox」。その編集委員である若林と小熊俊哉が、音楽シーンのキーマンに話を訊く新たなトーク配信企画が「Behind the Scene」だ。
「Behind the Scene」の第2回は、『音楽が未来を連れてくる 時代を創った音楽ビジネス百年の革新者たち』(DU BOOKS)の著者・榎本幹朗を迎えて、「音楽の最先端からビジネスと社会の未来を見通す」というテーマについて語った。『音楽が未来を連れてくる』は、音楽産業が産声をあげたトーマス・エジソンの時代から、サブスクリプションサービス全盛期の現在、最新の音楽ビジネスを扱う中国企業テンセントが提示する未来まで、音楽のビジネスモデルとテックイノヴェーションの関係性について見通した大著。榎本は、音楽産業はイノヴェーションによって何度も危機を乗り越えてきた、と語る。
本稿では、その「Behind the Scene #2」のダイジェストをお届けしよう。全編は、ぜひYouTubeのアーカイヴでご覧いただければと思う。
【動画を見る】「Behind the Scene #2 榎本幹朗」YouTubeアーカイヴ映像
榎本幹朗(えのもと・みきろう)
1974年東京生。作家・音楽産業を専門とするコンサルタント。上智大学に在学中から仕事を始め、草創期のライヴ・ストリーミング番組のディレクターとなる。ぴあに転職後、音楽配信の専門家として独立。2017年まで京都精華大学講師。寄稿先はWIRED、文藝春秋、週刊ダイヤモンド、プレジデントなど。朝日新聞、ブルームバーグに取材協力。NHK、テレビ朝日、日本テレビにゲスト出演。
サブスクが救世主になるまで
若林:今日は「blkswn jukebox」の新シリーズ「Behind the Scene」の第2弾ということで、『音楽が未来を連れてくる 時代を創った音楽ビジネス百年の革新者たち』の著者・榎本幹朗さんをお迎えします。榎本さんとは、『WIRED』の特集「これからの音楽」(2014年)でご一緒しました。今回『音楽が未来を連れてくる』の帯文を書かせていただいて、非常に光栄でした。
榎本:素晴らしい帯文を書いていただきました。「テックイノヴェーションの最前線は『音楽』にある。この100年ずっとそうだったし、これからもそうだ。音楽ビジネスが見えないあなたは、デジタルビジネスすべてから取り残される」。
若林:音楽が最初に新しいテクノロジーを活用して、映画など他のカルチャーがそれを追いかけていく、という印象があるんですよね。
榎本:2017年から、サブスクブームが起こったじゃないですか。サブスクって、たぶん音楽がいちばん早いんです。アメリカのメジャーレーベルが先導して、定額制ストリーミングサービスが誕生したのが2001年末頃。それに先駆けたのがファイル共有のNapsterで、今では当たり前になった「聴き放題」を初めて人類にもたらしたのはNapsterでした。それが、音楽の聴き方すら変えてしまった。Napsterの生み出した聴き放題をいかに合法化するか、と考えて「ストリーミングのサブスク」という答えに音楽産業は20年前にたどり着いた訳です。
でもその頃、サブスクはうまくいきませんでした。今はレコード会社にもCTOがいますが、当時はコンテンツ屋だったので、テクノロジーに関して素人だったんです。しかも、レコード会社同士で喧嘩して楽曲を融通し合わなかった。それでスティーヴ・ジョブズがiTunes Storeを提案してうまくいったので、サブスクはオワコン扱いとなり日の目を見なかったのですが、Spotifyによってサブスクブームが起こった。そういう流れです。
サブスクを復活してくれたのがiPhoneで、iPhoneによってニッチなサービスだったサブスクが突然、救世主になった。僕は2000年頃からライブ配信や音楽のストリーミングに関わっていたのですが早すぎて、うまくいきませんでした。未来が見えていても、それを実現するハードウェアがいつ誕生するか、見えていなければ意味がないんです。僕はクリエイター上がりの人間だったので、その考えがありませんでした。この本は「あの時どうすれば上手くいったのだろう」といろいろ学んでいくうちに勉強した結果です。
スティーブ・ジョブズ、〈さようなら、そして、ありがとうiTunesーー音楽をデジタル時代へと牽引したAppleの功績〉より(Photo by Paul Sakuma/AP/Shutterstock)
若林:過去についても同じことを言えるのでしょうか?
榎本:そうですね。1930年頃、アメリカでラジオが普及し始めました。ラジオは元々軍事の無線技術でしたが、「放送の父」と呼ばれる(デイヴィッド・)サーノフが無線機を普及させるにあたって考えたキラーコンテンツが音楽です。
その頃、エジソン・レコードという世界初のレーベルがあったのですが――エジソンって、レコード産業の父でもあるんですよね――、売上が下がっていました。当時の蓄音機は蝋管を使っていたので音が良くないのですが、ラジオはエレクトロニックなので音質の劣化がない。レコードの値段も今の感覚でいうと1万円ぐらいしたので、人々はそんなにたくさん買えなかったのですが、無料で聞けるラジオの方が音は良いし、コンテンツも豊富なので、音楽好きはラジオを買う、という流れになった。
結果、ラジオの普及によって、レコードの売上は25分の1になりました。インターネットによる音楽不況を遥かに超えたインパクトだったんです。その後20、30年かけて音楽産業はイノヴェーションを重ね、レコードは持ち直したわけです。だから、後輩の僕らも、イノヴェーションを生む創造性を忘れなければ、どんな危機が来ても復活できるんだ、勇気を持って、ということを書いたのがこの本の第1章です。
技術=イノヴェーションではない
若林:この本で一番伝えたかったメッセージは、強いて言えばどういうことでしょう。
榎本:音楽産業には何度も危機が訪れていますが、イノヴェーションによって乗り越えている、ということです。
音楽産業は今、パンデミックで最もダメージを受けている産業の一つですよね。でも、歴史を振り返ると、新しいものを作ることで必ず乗り越えている。文化産業の中でも音楽が最初に酷い目に遭うので、音楽産業の危機は常に前例がないから、自分で新しい答えを作っていくしかなかったんです。今の危機に対する新しい答え――僕はそれを「ポストサブスク」と呼んでいます――を音楽産業が作ろうとしているんですね。その例を最終章に載せています。
世界でSpotifyが流行っているからと日本も真似をして追従しましたが、そういうマインドでは新しい答えを作れません。僕は2012年からサブスクの旗振り役をやりながらも、日本の問題はサブスクだけでは解決しないとも言ってきました。「サブスク+αを作っていきませんか」と訴えていたのですが、ずっとスルーされていました。
〈音楽業界の未来、実はストリーミングではなくSNSが重要〉より(Photo by Griffin Lotz)
若林:この本では、70年代後半から80年代にかけてソニーが果たした役割や、iモードにおける着メロから着うたへの変遷を通して、日本の先進性についても熱を込めて語られていますよね。
榎本:おっしゃるとおり、もうひとつのテーマは「日本」です。欧米の音楽産業はサブスクで黄金時代を取り戻せるかもしれませんが、日本には再販制度があってCDの値段が高いので他国と差がある。さらに欧州の月額10ユーロ(1300円)と比べて月額980円と低くなっている。これを埋める新しいモデルを作ることが、日本に課された責務です。
ただ、日本はアメリカにも中国にも負けた、自分たちはもう新しいものを作れないと思い込んで、心が折れている状態です。でも、携帯ラジオやウォークマン、CDを生み出して世界の音楽産業を変えたのは日本のソニーでしたし、サブスクブームを作ったiPhoneが誕生したきっかけも日本でした。
パソコンで利用するインターネットは基本的に無料サービスの世界ですが、スマホでは有料サービスが通用する。その先駆けがiモードなんです。日本人は「ガラケー」と自虐していますが、日本のケータイは欧米で初期スマートフォンに分類されています。
さらに、iモードって月額300円のサブスクですよね。iモードは『とらばーゆ』の元編集長・松永真理さんが雑誌のビジネスモデルを応用して始めたもので、都度課金もやりたいと「着うた」を作ったのがソニーミュージックの今野(敏博)さんです。モバイルで音楽配信をやる「音楽携帯」「ウォークマン携帯」でiPodやiTunesに勝とうとしたのがソニーの戦略でした。実際、日本のiTunes Storeの売上は着うたの20分の1だったので勝っていました。日本はすでにiモードの時点で「サブスク+α」すら実現していたんですよ。
この日本での敗戦が世界中に広がりかねないと、ジョブズが危機感を持ち、「携帯を作ろう」と考えて生まれたのがiPhoneでした。日本はモバイルとモバイルコンテンツを切り開いたのでモバイル先進国と呼ばれていましたが、それに対してリープフロッグを仕掛けたのがジョブズだった。
この流れは全て技術的なロードマップに沿って起きていました。まず携帯電話の第1世代(1G)はアナログ配信でした。ここでアメリカが携帯電話を生んだ。第2世代(2G)はデジタル化で文字や画像が携帯電話で扱えるようになり、ここで日本のドコモがiモードを生み、モバイルとインターネットを結びつけて、アメリカにリープフロッグを仕掛けました。
第3世代(3G)は携帯電話のブロードバンド化だったのですが、初期はまだ動画を扱えるほど回線が太くなかったので、まず音楽、着うたでドコモにリープフロッグを仕掛けたのがauでした。auと組んだソニーはそのまま音楽ケータイで、iPodにもリープフロッグを仕掛けようとしていた。
しかし技術ロードマップは3Gの後期に差し掛かり、動画も携帯電話で見られる時期に入ろうとしていました。さらにCPUも、ノートパソコンよりも小さなデヴァイスが実現できるまでに、省電力化が進んだ。このCPUと通信速度の技術ロードマップの両方を使って、日本のエレクトロニクス産業にリープフロッグを仕掛けたのが、ジョブズのiPhoneだった訳です。
iモードがもたらした転回
若林:この本には、iモードがローンチの記者会見を2回やった話が出てくるじゃないですか。1回目は鳴かず飛ばずで、2回目に広末涼子さんを投入して、女性がiモードの普及のドライヴァーになった。イノヴェーションはエンジニアドリヴンで、下手すると男性目線で語られてきたわけですが、女性主体で広まったことの好例ですよね。
榎本:広末涼子さんは高校生の頃にポケベルのCMに出演していました。ポケベルは元々業務連絡用の機械でしたが、それ以降女子高生たちがコミュニケーションに使い始めた。ポケベルによるコミュニケーションのアイコン的な存在になった広末涼子さんにiモードでもアイコンになってもらおう、とドコモは考えたわけです。
広末涼子が出演したiモードのCM
若林:今にして見れば、そこで起きた転換は、男性原理的な「コンテンツ空間」を、女性主導の「コミュニケーション空間」にスライドさせたように見えるんですね。iモードは、世界に先駆けてそれを提示したのかもしれない。受け手がサービスの構造を変えていく可能性があることは重要だと、改めて思いました。
たとえば、K-POPの受容のされ方と、ファンダムのテクノロジーの使い方やネットワーク化のされ方は、今までの男性的なファンのコンテンツ受容とは異なるプロトコルが作動していると思います。これは無理に「男性/女性」と言わなくてもいいんですが、垂直から水平、コンテンツからコミュニケーション、そういった価値軸の転換ですよね。
榎本:あるいは理性に対する感性、左脳に対する右脳とも言えるかもしれません。iPodはそれを使ってソニーのウォークマンに勝ちました。ジョブズは日本でiPodを売る戦略を元ソニーの前刀(禎明)さんに訊いて、ファッション路線で女性にターゲティングすることを提案された。それで、iPod miniやiPod Shuffleをファッションアイテムとして銀座のOLにターゲットしたら当たった。いわゆる感性マーケティングです。
若林:そこが、実は日本が得意な分野である可能性があるな、と本を読みながら思ったんですよね。日本はとかく「技術」が自分たちの得意分野だ、と思いがちですが、実はそこではないのかもな、と。
榎本:そうですね。イノヴェーションは「=技術革新」ではなく、「技術革新+クリエイティヴィティ」なんです。そのクリエイティヴィティの部分が「感性」というか。日本は女子学生やOL、おばさんがブームを起こすことが伝統的に多い。感性マーケティングに強い国ですが、その強みを忘れかけている気がします。
そこで、最終章で扱ったのが中国のポストサブスクです。
音楽はサブスクで先頭を切ったのですが、サブスク一辺倒。だけど、ゲーム業界にはサブスクもパッケージもあって、スマホゲームには都度課金=マイクロペイメントもある。多様なビジネスモデルを作っていて、ゲーム業界は音楽産業をリープフロッグしていた。そこで、音楽サブスクへの「プラスアルファ」は、スマホゲームが成功させたマイクロペイメント=都度課金になるだろうと僕は思っていました。中国の音楽サブスクはこれを実現したんですね。
中国のテンセント・ミュージックという巨大音楽企業の売上は、3割が広告やサブスクで、Spotifyと同じビジネスモデルです。ですが、「ソーシャルエンターテインメント」なるものが70%の売上を占めています。中身は、日本では「投げ銭」、英語では「ギフティング」と呼ばれるものでした。つまり、かわいい女の子がカラオケで歌って、フォロワーたちがギフティングで貢ぐ、という仕組みがサブスクと結びついているのです。
〈中国版SpotifyのTencent、米国株式市場へ上場〉より(Photo by Spencer Platt/Getty Images)
小熊:現在の音楽業界ではあまり見ないですよね。
榎本:日本ではメジャーアーティストのカラオケ音源で「歌ってみた」をやったら怒られますし、稼いだら裁判になる。中国は著作権管理が甘いので、素人がカラオケ音源で歌って視聴者がギフティングするビジネスができた。
きっかけは「YY」というゲームのライブ配信サイト/チャットルームでした。2012年頃、社内で調査をしたら、ゲームの話をせずに、かわいい女の子がカラオケをやって視聴者がそれを見ている、という状態だった。それで、試しにバーチャルカラオケコンテストのチケットを会員向けに無料で配ったら、チケットがオークションサイトで高額で売買されていた。お気に入りの女の子を優勝させるために投票権を買いたいユーザーがいたわけですね。それで、「これはいけるんじゃないか」と中国人たちが気が付いた。日本のLINEスタンプを真似て、プレゼントに贈るスタンプを売ったんですね。あまり大きい金額が動くと共産党政府に怒られるかもしれないので、1回あたりの上限を200万円にした。200万円を投げ銭するユーザーはいないだろうと考えていたら、それがたくさんいたと。
若林:すごいな……。
榎本:そこから「ソーシャルカラオケ」のブームが始まった。中国のサブスクアプリを立ち上げると、ニコニコ動画のように文字がジャケットの上を流れます。その後ろにLINEスタンプみたいなものが付いていて、それを売っているわけです。
しかも、プレゼントのボタンが再生ボタンより目立つように置いてあって、その次にマイクのボタンがある。マイクのボタンを押すとアプリがボーカルをカットしてくれるので、自分で歌ってアップロードして友だちとシェアできる。友だちは、それに対してギフティングする。

これにハマったのが地方都市の50、60代のおばちゃんたちでした。あるおばちゃんが歌って、友だちのおばちゃんが「すごい」と換金可能なギフティングのスタンプを互いに贈り合うと。この状況は予想外ですね。
「YY」ホームページより
若林:カラオケは最初からソーシャルなものであると。コミュニケーションとして音楽を使う、という。
榎本:着うたもそうで、つまり、音楽を使って遊ぶということですね。音楽産業は今まで「音楽を聴く」ことをマネタイズするために、著作権や原盤権を使ってきました。CDもサブスクもそうです。けれど、これからは著作権や原盤権が「音楽でコミュニケーションする」のをどんどん活性化させる方向に行かなければならない。これもポストサブスクの流れです。
しかも歴史を振り返れば、その大本は日本が生み出したんですよ。カラオケって日本の発明ですし、90年代のCD黄金時代は、シングルを買ってカラオケの練習をして、みんなで集まってカラオケ歌う、という仕組みがあった。それをデジタルでやったのが中国です。この中国のギフティングについて、ゴールドマン・サックス証券のアナリストが「AKB48の握手券商法のデジタル版だ」と言っています。そういうビジネスモデルを作ったのも日本だったはずです。
僕が提案しているのは、「これを合法的にやりましょう」ということ。合法的にやることで、レコード会社とアーティストに売上が配分される。中国はサブスクにC to Cを導入するということを発明した訳です――友だちどうし、素人とファンがお金のやり取りをするというカスタムですが、もし日本でやるなら原盤権を処理する必要があります。たとえば、カラオケ音源を使って歌って利益を上げたら、その3割を配信業者へ、3割をレコード会社へ、4割を歌い手に配分する。僕はそういう提案をしています。
先ほどの「かわいい女の子に200万円を投げ銭する」というのは、正直に言って品のない話です。ただ、その本質は重要です。人間は、応援したいものに対してお金を払いたい、助けたいんですよ。だから、それがアーティストであってもいい。そもそもアーティストはそういう職業ですから、それを有効に使えばいいんです。
ポストサブスクの鍵は「エンゲージメント」
榎本:僕は、ポストサブスクの核のひとつは、音楽をただ聴くのではなく、楽しむことに使うことだと思います。もうひとつは、アーティストへのエンゲージメント、愛情表現をする場を用意すること。
今の時代、CDは買わなくていいわけですが、わざわざそれを買ったり、ライブ会場でTシャツやタオルを買ったりするのは、それしか愛情表現の方法がないからですよね。その愛情表現をする場を、もっとテクノロジーを使って作っていかないといけない。それがポストサブスクの使命のひとつです。
中国の真似をしよう、と言いたいわけではありません。アメリカも中国のポストサブスクに気づきながら、真似はしませんでした。中国に刺激を受けながら別のことをやろうと考えたのが、「Sessions」のファウンダーの1人であるティム・ウェスターグレン。
Pandoraを作った彼がPandoraを辞めた後にゲームビジネスを手伝ったら、ビジネスモデルが音楽よりも豊富で先に進んでいることを知った。また、中国ではライブ配信がコロナ禍よりずっと前からブームになっていて、ゲームで始まったライブ配信が音楽をきっかけに巨大ブームになっていた。ティム・ウェスターグレンは「これだ」と思ったわけです。
彼はサブスクに近い広告モデルのPandoraを作って、無名のミュージシャンが10、20万人のオーディエンスを得ることに成功した。ですが、それを収益化する場を作れなかった。そこで中国のギフティングを知って、これこそサブスクでも出来なかった、ミュージシャンの活動を収益化してあげられる何かではないかと気づきました。
彼が始めたSessionsはライブ配信のプラットフォームですが、さらに「プロモーションエンジン」というものを作った。それが、他のSNSにアーティストの宣伝を広告出稿してくれるんです。原資はオンラインチケットやギフティングの売上。売上は3割がApple税で、3割がSessions、残りの4割がアーティストに配分されますが、Sessionsがもらう3割はアーティストの宣伝費になります。それでレベニューシェアしましょう、という仕組みを作ったんですね。
ティム・ウェスターグレン、〈アーティストが稼げる音楽ストリーミングサービスとは? 米パンドラの創業者が語る〉より(Photo by Theo Wargo/Getty Images)
小熊:このサービスはいいですよね。
榎本:ファンが応援するために「いいね」をしたりツイートしたりしますが、要するにそれは広めたいということです。お金を直接渡すよりも、そのお金がアーティストの宣伝になる方が嬉しいはず。「このアーティストを他の人にも好きになってほしい」というエンゲージメントの中でも強い思いを後押しする――Sessionsが作った仕組みはそれです。中国の投げ銭をそのままアメリカに持ってきても受け入れられない。ギフティングするファンと受け取るミュージシャンの間に、もっと美しい関係を創る必要があると考え、ギフティングすると、そのお金が大好きなアーティストの宣伝になる、という構図を作り出した。
つまりティム・ウェスターグレンは、中国の真似をしなかった。ミュージシャンが音楽で生活できるようにしたい、という高い志から、クリエイティヴな発想が出てきたんです。クリエイティヴっていうのは、そういうことだと思います。
「Sessions」の様子
若林:先ほどの投げ銭をするタニマチの話は、かつて音楽家がパトロンの貴族に抱えられていたようなことで、それ自体が束縛になることもある。そういう部分が剥き出しになっているのは、ちょっと怖いですよね。
榎本:そうですね。美しくない。
若林:それを、直接的な金銭のやり取りにだけにならないようにするプラットフォームの設計は重要ですよね。
榎本:はい。つまり、アーティストとファンとのコミュニケーションを、より美しいものにしたい。これも、クリエイティヴなイノヴェーションを起こすドライヴァーになりえます。
たとえば、iPhoneという指先だけで操作できる美しいデバイスが生まれたのは、それ以前の携帯電話がボタンだらけであまりにも醜い、と美意識の強いジョブズが感じていたからです。「美」は、クリエイティヴのドライヴァーになると思います。
音楽はどれほど大衆化したとしても、美を扱っている芸術です。だから、ファンとアーティストの美しい関係をどうやって作っていくか。それが、中国が出した素晴らしいオリジナルな答えに対して、日本がそれをより美しいものにしていく際のドライヴァーになる。
若林:ブロックチェーンで音源やりとりする、あるいは限定コピーを作るといった可能性はいかがですか?
榎本:ありえますね。ブロックチェーンが素晴らしいのは、コピーを潰す技術だということです。だから、限定100枚のアルバムをブロックチェーンの技術で配ったら、コピーが限定された、絵画のような価値を持った芸術品になりえますよね。それにプレミアムな価値を付けて、ファンどうしで転売するたびにスマートコントラクトによってアーティストやレコード会社に売上が入る仕組みを作ることも可能だと思います。デジタルデータに価値に付かないのは無限にコピーできるからですが、コピー数を限定するテクノロジーが登場したので、それはどこかで使えると思います。
若林:そうですね。そういう作品だけを扱うアートギャラリーみたいなものがあってもいいのかも知しれない。
小熊:この本がすごくいいのは、音楽や芸術の価値付けの捉え方を考え直そうよ、と書かれているように思えたところでした。
若林:僕らが音楽をどう生活の中で価値付けているか――音楽をただのBGMとしてしか使わない人もいるだろうし。それが、サブスクによって問われることになった。サービスが変わることで、自分たちと音楽との距離も変わる。そこが面白いですよね。
楽器をめぐる革新
榎本:音楽産業のビジネスモデルとは別に、肝心の音楽そのものはテクノロジーによってそんなに変わっていません。なぜなら、ここ四半世紀でITは飛躍的に進みましたが、楽器自体を変えるものとしてそのテクノロジーを使えていないからです。ただ、歴史的にテクノロジーが楽器を変える瞬間は必ずある。僕の本の最後の方で触れていますが、たぶんIoTが楽器を変えると思います。ユーザーインターフェースのAIが追究されることで新しい楽器ができて、新しいメガトレンドが出てくると思います。そこは僕ももっと知りたいことですね。
これまでサンプラーやシンセサイザーが登場しましたが、キーボードであるとか、ユーザーインターフェースの部分は変わっていない。そこを変えるものができたら、新しい時代が始まるのではと。たとえば、物理モデルによって現実にはありえない楽器を想像して、それをバーチャル空間で音を鳴らすことはできますが、その可能性を引き出すインターフェースはまだありません。もしかしたら、手を使わないブレインユーザーインターフェースになるかもしれないですね。
小熊:そうなると面白いですよね。テクニックから解放されるわけですから。
若林:エレキギターやサンプラーの登場は一種の民主化で、それ以前は訓練を受けた人間しか楽器を演奏できなかったのが、新しい楽器によってそうではなくなったわけだよね。ただ、新しい楽器が広まっても、オリジナルの新しい音楽を作る方向に行くとは限らない。
榎本:僕、時々こういう夢を見るんです。音楽が鳴っていて、こういう感じがいいなって考えると、音楽がいい感じに変わるんですよ。そうやって夢の中で作曲らしきことをやって、感動して目が覚めると涙が流れていたりします。そんな風に、「強いAI」が誕生するとプロデューサー的な制作を誰でもできるようになるかもしれないですね。
小熊:音楽のいいところは、音楽を奏でられなくても、音楽というカルチャーに参加できるところです。たとえば、レビューを書くとか。先ほどのソーシャルエンターテインメントは、それに近いものではと。
若林:そうそう。グレイトフル・デッドのコミュニティではファンがライブテープをシェアする。K-POPはアーティストが投下するネタを元に動画を自分たちでつくったりしてコミュニケーションしていく。ファンが参加してカルチャーを作っているわけですよね。
榎本:インターネットの登場以降、ファンが「いいね」ボタンを押すだけになってしまったことに不満があります。若林さんのように言語化能力に長けていない限り、普通のリスナーは音楽の素晴らしさを言語化できないわけですが、ネットは基本的にテキストのコミュニケーションになってしまっている。でも優れた作品に触れて感じたことをラブレターのように文章化することは、我々みたいな一般人にはむずかしいから、すべてが「いいね」やスタンプに収斂していったんです。だから「リスナーが音楽を聴いて感じたことを、もっと豊かに表現できる仕組みはないのだろうか?」とずっと思っています。
VR技術が発達が進んだら、友だちとしゃべりながら音楽を聴いて、「いいよね」「そうだよね」と不完全な言語でも感覚を共有できる空間を作れるかもしれません。でも、スマートグラスのサイズや品質が、閾値を超えるまで難しいでしょう。それまでは映像ではなくて音でVRによるコミュニケーションを作る方向に行くのが、歴史的にも正しいかもしれませんね。クラブハウスのブームを見ていて、そう感じます。
本のタイトルにした「音楽が未来を連れてくる」というのは、映像よりもデータ的にもハード的にも軽い「音」からイノヴェーションは始まってきた、ということでもあるのです。
『音楽が未来を連れてくる』
榎本幹朗・著
DU BOOKS
発売中
公式ページ:https://diskunion.net/dubooks/ct/detail/DUBK284
blkswn jukebox: Behind the Scene #2 榎本幹朗「音楽の最先端からビジネスと社会の未来を見通す」
2021年2月12日(金)開催
会場:blkswn welfare center(黒鳥福祉センター)
主催:blkswn jukebox(黒鳥社)
協賛:うぶごえ(ubgoe)
撮影:間部百合
音響:山口宜大(Magic Mill Sounds)
制作:宮野川真(Song X Jazz)