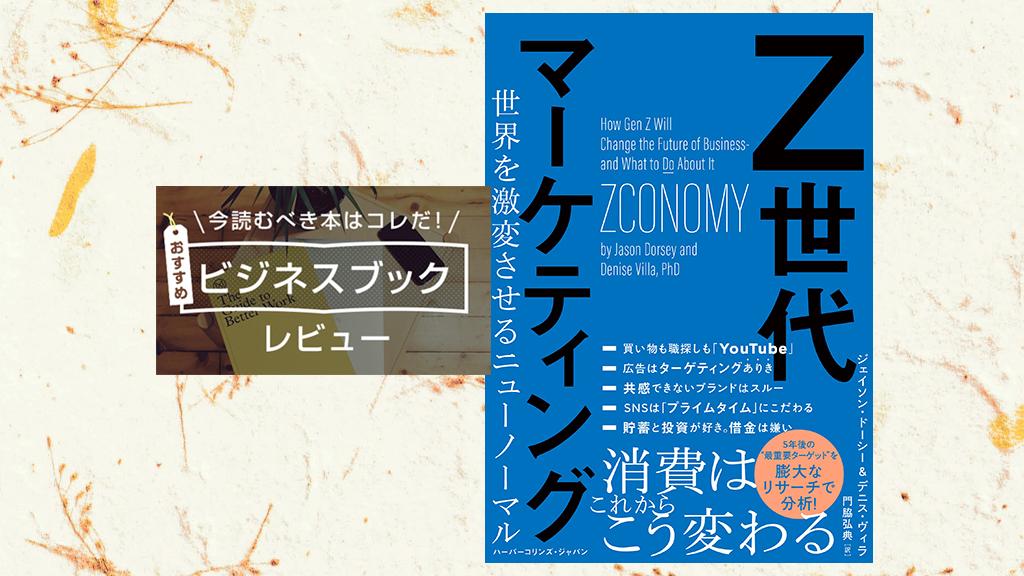本稿はKDDIが運営するサイト「MUGENLABO Magazine」に掲載された記事からの転載
課題とチャンスのコーナーでは、毎回、コラボレーションした企業とスタートアップのケーススタディをお届けします。
昨年のCESで大きな話題となったスマートコンタクトレンズ企業の「Mojo Vision」は、砂粒程度のディスプレイを実際のコンタクトレンズに埋め込んで装着を目指す意欲的なプロダクトです。コンセプトとしては2010年の半ばあたりからSamsungやGoogle、Sonyなどが取り組みを公表しているもので、Mojo Visionもその最中の2015年に創業されています。
彼らはコンタクトレンズに装着できるほどの極小で密度の高いダイナミックディスプレイ技術を保有しており、コンピュータービジョン用に開発された超省電力のイメージセンサー、高帯域幅の低電力無線通信器、高精度のアイトラッキングおよびぶれ補正用モーションセンサーなどの研究を進めてこのプロダクトの実現に向かっています。
日本との関わりではKDDIが運営するKDDI Open Innovation Fundからの出資(2020年)があったのですが、それに続いて昨年12月には国内大手コンタクトレンズ事業のメニコンとスマートコンタクトレンズに関する共同開発契約を締結したと公表しました。今回の契約により両社は、スマートコンタクトレンズの商用化に向けたフィジビリティ・スタディを開始するとしています。
国内大手と新進気鋭のグローバル・スタートアップがどのような経緯で共創に至り、協力してどのようなハードルを越えようとしているのでしょうか。その裏側を両社にお伺いします。前半ではMojo Vision社のプロダクトや目指すビジョンについてまとめ、後半はメニコンでこの共創に取り組むチームのお話を共有したいと思います。
現実世界に仮想のコンテンツを重ね合わせるAR(拡張現実)の世界観は、映画「レディ・プレイヤー1」にあるように古くからサイエンスフィクションの文脈で語られてきました。一方、スマートデバイスの登場で、例えばポケモンGOや、SnapなどのサービスでARコンテンツは身近になりつつあるのも事実です。
ではスマートコンタクトレンズは現在、どのような目的で、どこまでが実現しているのでしょうか。
Mojo Visionが目指すのは、極めてシームレスに現実世界に仮想コンテンツを重ね合わせる世界観です。スマートコンタクトレンズを装着していれば、視線をスマホに落とすことなく、対象になる人の情報を示すことができます。また、コンタクトという特性上、常に装着していることからバイタル情報を取得しやすい性質があります。
スマートコンタクトレンズ全般にいえる事業可能性として、例えば基礎疾患を持った方が装着した場合、血糖値などの情報をいちはやく他人に伝えて適切な処置を依頼することが可能になる、といった具合です。つまり装着している本人だけでなく、それを見ている側に対してもすばやく情報提供ができるのです。
Mojo Visionはこの世界観を「インビジブル コンピューティング」と表現していました。どの場所にいってもまるで地元にいるかのような体験を提供し、現実世界の「見た目」を変えることなく世界と関わることができます。
創業者のDrew Perkins氏は、かつて自身の目に発生した健康問題をきっかけにこのプロジェクトを考えついたそうです。その後、サンマイクロシステムで3Dグラフィックの研究をしていたMichael Deering博士と出会い、人間の目と同じ生物学的解像度を保ちつつ、必要とする演算能力や消費電力を大幅に抑えることができる技術の開発に成功します。
人類が60年かけて歩んできたコンピューティング、インターネットのデジタル世界はスマートフォンの登場によるモバイルシフトを経て、新しい世界観を求めるようになりました。多くの研究者、企業、消費者はその先にある世界が仮想現実であると予想しており、没入の具合によってVR・AR・MRのいずれかの体験がいずれ必要になると各種開発を続けています。

アニメの世界だったユビキタスの世界観は、今年のCES2021で多くのARグラスが登場してきたように、もう一般消費者の手元に届きつつあるのです。
一方、VRやAR、MRといったxRデバイスの多くは大きな「被り物」を必要とします。そこでMojo Visonはその課題をコンタクトレンズという手法で解決しようとしました。データを表示させるだけでなく、普段は普通のコンタクトレンズとして視界を遮らず、消費者や小売、政府、視覚障害者など幅広い人たちをターゲットにした新しい情報体験を提供しようというのです。
ただ、最初から全てを対象にするのではなく、初期のユースケースには「アンメットニーズ」を想定しているそうです。例えば火災現場に突入する消防士に適切な情報を提供したり、緊急医療の現場や両手が塞がるネットワーク技師、アスリート選手の競技中や練習でのパフォーマンス情報など、これまで満たされていなかった情報提供の現場を想定してこの未知のデバイスを検証するとしていました。
また、機能をオフにした状態でも通常のコンタクトレンズとして使えることを目指すため、グローバルで数億人いるという「コンタクトレンズ利用者」もターゲットになります。ゆくゆく、一般消費者が利用できるような汎用ナビゲーションサービスが実装されれば、まずはこれらのコンタクトレンズ利用ユーザーが対象になる、という考えです。
ではここからMojo Visionが開発中のスマートコンタクトレンズの仕組みについて、今、わかっている範囲の情報を共有します。
企業として創業してから5年、構想はそれ以上前から技術調査を行っていたこのスタートアップは、現在、100名を超える従業員を抱え、これまでに1.59億ドルを調達しています。従業員の大半は博士号を持つ研究者や開発者であり、これまでに110以上の特許を取得しています。
Mojo Visonの開発するスマートコンタクトレンズはディスプレイ、無線通信、センサー、材料、すべてにおいて研究開発を進める必要があり、このようにして開発した極小のディスプレイやセンサー、バッテリーを強角膜レンズ(※)に収める必要がありました。ディスプレイは角膜には触れない仕組みになっていて、強角膜レンズの強敵である酸素供給についても最大化する特許を取得しています。
※強角膜レンズは角膜(黒目)から、強膜(白目)まで覆うレンズ。スマートコンタクトレンズでは眼球をより大きくカバーする必要があり、この世界有数の技術を保有している日本のメニコンと昨年末に提携している
強角膜レンズに配置されているバッテリーは省電力で、現時点ではワイヤレス充電を想定しているそうです。またセンサーは眼球の動きを捉えるモーションセンサーと、イメージ検出に使われるコンピュータービジョンが埋め込まれます。
そしてこの中央には0.5mm未満のサイズでテキスト、写真、ビデオを再生できるディスプレイが設置され、この上に薄い1枚のプラスティック膜を光学系として置くことで、ディスプレイから直接網膜に映像を映し出すことができる仕組みになっています。
ディスプレイは極めて網膜に近く、装着する人の視界を遮らないそうです。また現在は緑色のみのディスプレイですが、カラーバージョンも開発中とのことで、両眼に設置できるため立体視ができるというお話でした。
さて、気になるのはどうやって操作するのか、という点です。
この方法についてMojo Visionはポインティングデバイスとしてアイ・トラッキング、つまり目の動きを採用したそうです。Mojoのスマートコンタクトレンズは最初、「中継装置」と彼らが呼ぶ、ウェアラブルのデバイスと連動して動くことが想定されています。
この中継装置に対してレンズが捕捉した眼球の動きを送信し、10ミリ秒以内にレンズに送り返します。これにより、眼球の動きは常にレンズが把握するため、見ている位置が動いてもコンテンツは正しい位置に配置されるほか、この目の動きそのものがポインタデバイスとして使えることを考えているそうです。またこの中継装置は他のスマートフォンやクラウドなどと通信も可能で、ここを通じて最初はさまざまなサービスと連動するというお話でした。
ここまではMojo Visionが開発したスマートコンタクトレンズの現在地について、同社の説明を元に解説してきました。後半は昨年、衝撃的な提携発表をした国内コンタクトレンズ大手のメニコンのチームになぜ彼らだったのか、その共創の背景を伺います。
BRIDGEでは会員制度「BRIDGE Members」を運営しています。会員向けコミュニティ「BRIDGE Tokyo」ではテックニュースやトレンド情報のまとめ、Discord、イベントなどを通じて、スタートアップと読者のみなさんが繋がる場所を提供いたします。登録は無料です。