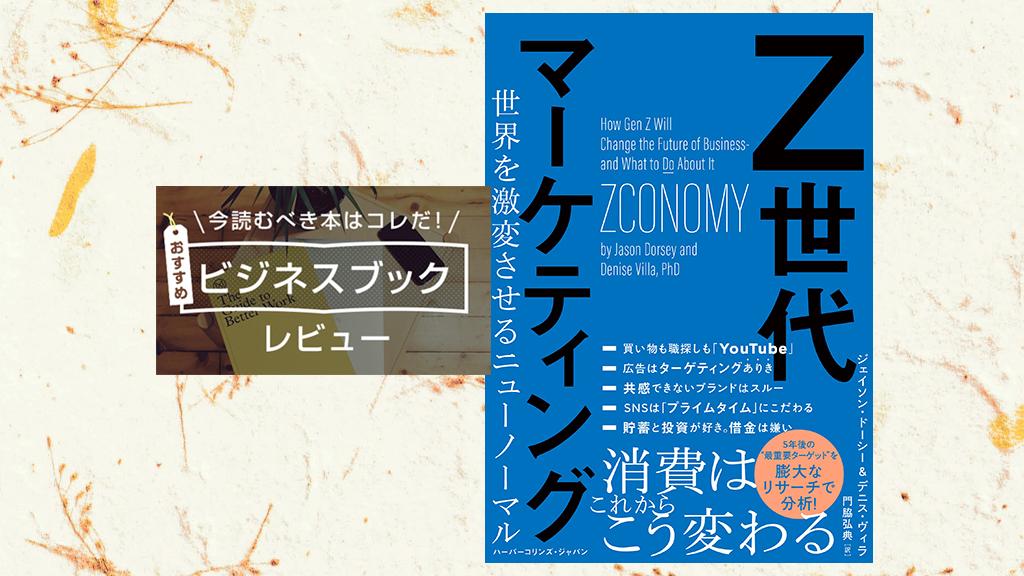15歳、才能だけを頼りに徒手空拳で単身イギリスへ! そのあとは……!? いまや「世界でもっとも演奏機会が多い」現代作曲家・藤倉大の超絶オモシロ自伝エッセイ『どうしてこうなっちゃったか』から、試し読みをお届けします。※ 記事の最後に、藤倉大さんの貴重なオンラインイベント(いよいよ本日! 2022年3月16日19時半~)のお知らせがあります。お見逃しなく。
* * *
すったもんだあったが、無事、王立音楽大学大学院に入学した。2000年9月のことだ。大学院での作曲の先生はエドウィン・ロックスバラだ。
エドウィンは、何から何までダリルとは正反対の作曲家で、イギリスの主要オーケストラで多くの現代曲を振る指揮者としても活躍し、かつては同時にサドラーズ・ウェルズ・オペラ(現在のイングリッシュ・ナショナル・オペラ=ENO)の首席オーボエ奏者でもあり(同時期にエキストラ奏者としてBBC交響楽団にもよく参加していたんじゃないかな)、多くの現代曲をレパートリーにして紹介に努めた。ベリオの「セクエンツァVII」やハインツ・ホリガー(1939年生まれのスイスのオーボエ奏者、作曲家、指揮者)の「カルディフォニー」のイギリス初演もエドウィンによる。
そんな彼には、ソリストとオーケストラのための協奏曲や、合唱とオーケストラなどシンフォニックな作品が多い。僕が特に好きなのは「クラリネット協奏曲」(1995年)と「サターン(Saturn=土星)」(1982年)だ。「クラリネット協奏曲」はソロと同じくらいオーケストラが忙しい、「オーケストラのための協奏曲」のような側面を持つコンチェルト。そして、ソロのクラリネット・パートも、木管楽器には特別に詳しい、さすがというべき書法で、洗練の極み。「サターン」は分厚くオーケストラが鳴っていると思ったら、そこに高音のキラキラした音がからみ合ってゴージャスで強烈なサウンドがうねり響き、初めて聴いた時は、そりゃほれぼれしたものだ。
ダリルはジャズやポップスと深く関わっていたが、エドウィンがクラシック以外の音楽の話をするのは聞いたことがなかった。
エドウィンはクラシックの電子音楽の世界でも先駆者で、頻繁に演奏されたオーボエとエレクトロニクスの作品「……at the still point of the turning world……(……回転する世界の静止点で……)」など、まったく「イギリス風」を感じさせない、ヨーロッパ大陸的な響きが魅力の音楽だ。
そうなのだ。イギリスとヨーロッパ。この2つには大きな音楽的隔たりがある。音楽史的に見てみよう。
例えばエルガー(1857~1934年。イギリス)とドビュッシー(1862~1918年。フランス)。たった5歳しか違わないから、同時代の作曲家だといっていい。なのに、どう見てもドビュッシーの演奏回数のほうが、エルガーよりも1000倍、多いだろう。
他にも、ベンジャミン・ブリテン(1913~1976年。イギリス)とピエール・ブーレーズ(1925~2016年。フランス)は、一回り違うだけだが、たった12年の違いなのに、その音楽の響きは50年いや100年違うんじゃないかってくらいだ。もちろんブーレーズがより革新的だ。
この当時、僕は、イギリスの音楽にまったく関心がなかった。
ポーランドの作曲コンクールで優勝し、ワルシャワでの授賞式コンサートで演奏されたものの、あとはイギリス国内でしか僕の作品は演奏されていなかった。僕は、そんな自分の音楽状況が、大いに不満だった。
もちろん23歳で、BBCラジオで自分の作品が流れたり、ロンドン・シンフォニエッタを始め、他にもいろいろなイギリスのオーケストラが、僕の音楽を「国内の若手作曲家」として取り上げてくれたのは嬉しかったし誇らしかった。
そう。僕はいつも「英国の作曲家」として扱われていたのだ。いや、たしかに、そういう側面はある。日本の大学を卒業後、大学院生としてイギリス留学する人が多い中、僕は高校からイギリスで過ごしたのだから。イギリスが教育した作曲家と言われても間違いではない。
だが、僕はイギリスのクラシック音楽の系譜が好きじゃないのだ、自分でも困ったことに。
今なら思える。イギリス国内だけとはいえ、自分の作品が演奏、放送されていた。それでじゅうぶんじゃないか。それ以上、望むのは欲張りだろう。
だけど、当時は若かった。今のようにネットで情報がたくさん集められる時代ではなかった2000年の秋。ドイツやフランスのコンサート情報が掲載された音楽雑誌を書店で立ち読みし、さぞ刺激的な面白い音楽が大陸では聴けるんだろうな、と夢想した。
現在でも、多くのイギリス人作曲家の実感であるはずだ。作品が、なかなかドーヴァー海峡を越えては演奏されない。正確にいうと大陸で「認められない」のだ。
でも、ヨーロッパ大陸の人たちの気持ちもわかる。そりゃ僕じゃなくたって、みんなエルガーよりドビュッシーを演奏したいし、聴きたいでしょ。
話を元に戻すと、イギリス人でありながらヨーロッパ的かつ面白い音楽を書く例外的な作曲家がエドウィン先生なのだ。彼は、いつも美しい言葉遣いをする人で、しかも優しい。さらにヴィーガン(vegan)でもある。ヴィーガンだから単なるヴェジタリアン(vegetarian=菜食主義者)にとどまらず、乳製品、卵を含む動物性のものをまったく口にしない。奥さんも同じだ。
ある日、エドウィンのお宅に呼ばれた。これなら大丈夫だろう、とチョコレートのボックスを手土産にした。彼は、その時、ニコニコしながら「あっ、このチョコレート(ホワイトチョコではない、ただの黒いチョコレート)には、ミルクが入ってるみたいだね。でも、ダイが持ってきてくれたので、特別に食べるね!」と箱を開けて、僕の前で奥さんと一口だけ食べた。かなり厳格なヴィーガンなのだ。
さらに、彼は動物愛護活動にも熱心だ。
イギリス王室にはまだ狐狩りをする伝統がある。僕は特に動物愛護主義者というわけではないが、当時から、それでも狐を殺すのはどうかと思っていた。食べるわけでもなく、単にスポーツとしての狐狩りなんて。
だが、エドウィンは、そんじょそこらの愛護家ではない。彼は、誰かが狩りを始めようとする前にフィールドに赴き、狐を逃がすために太鼓や鉦(かね)を叩いて追い払って回ったことが、何度もあるのだ。そして、この対象は狐に止(とど)まらない。
エドウィンは、こういったプロテスト(抗議)行動で、過去数回の逮捕歴がある。抗議行動で警察に捕まる、というのはある種、芸術家の憧れであり箔
(はく)だ。その体験を最初のレッスンで誇らしげに話してくれたことが今でも忘れられない。
そういえばブーレーズも、「私は1回、逮捕されたことがあるんだよ」とニヤリとして語ったことを今、思い出した。2001年、スイスの警察がオペラハウス爆破計画の容疑者として勾留したのだ。有名な、週刊誌の記事での彼の発言「オペラハウスを爆破せよ!」(なんと1967年のもの!)が原因だった。もちろん大きなニュースになったので、クラシック音楽好きなら多くの人が知っている話だろう。
逮捕時のエピソードを語る時、エドウィンもブーレーズも目の奥が光る。イタズラ少年の笑顔になる。二人ともロックンローラーなのだ。
そしてエドウィンは、ブーレーズを崇拝していた。
エドウィンは、即興音楽や音楽の即興性を素晴らしいものだとは考えていなかった。どちらかというと嫌っていた。
その1点を見ても、ジョン・ケージを崇拝するダリルとは正反対な作曲家だ。
ダリルには、オーケストラを使った、クラシックの純音楽作品は少ない。彼は、自分が手がけたテレビ番組の音楽や商業音楽でオーケストラを使うことはあったが、それらを決して僕に聴かせてくれなかった。
昔、ダリルの家には猫がたくさんいた。演奏ツアーなどで出張がちだった彼は、自分の不在時の猫の餌やりのために、学生を自宅に住まわせていたことがあった。ベビーならぬキャットシッターだ。僕の友人がそのキャットシッターだった時、僕はよく遊びに行って、度がすぎるほど潔癖なダリルの、きっちり整理整頓された棚びっしりのDAT(デジタルオーディオテープ)や昔のカセットテープを漁(あさ)り、ずっと聴きたかったダリルのテレビ音楽を友人と鑑賞したものだ(ひどい生徒!)。ダリルは、仕事でやったテレビ音楽を、芸術音楽を目指す作曲科の学生たちにはあえて聴かせたくなかったのだろうが、僕はダリルの商業音楽が大好きだった。
ダリルの商業音楽は、今の商業音楽とは雲泥(うんでい)の差だ。現在は、ほとんど(か、あるいはまったく)音楽を勉強したことのない人が、サンプラーやシンセサイザーで、ちょこちょこっとオーケストラっぽい作品にした感のものが多いが、ダリルが商業音楽を作っていた時代は、本物のオーケストラを使って、オーケストラが演奏するにふさわしい曲を録音していた。当然、ダリルはきちんとオーケストラのスコアが書けるし、まして演奏家としても第一線で活躍していたので、音楽のクオリティそのものが違う。こう言うと彼は悲しむだろうが、僕は、ダリルの書く商業音楽と芸術音楽の質に、差はないと思う。特に商業音楽は、ジャズやポップスのプロデューサーかつプレイヤーでもあったので、その音楽性とオーケストレーションが冴(さ)えわたっている。
ダリルが1980年に作った商業音楽の1曲が、2001年に出た、ゼロセブン(Zero 7)というアシッドジャズ系の2人組ユニットのデビューアルバム「シンプル・シングズ(simple things)」の最終トラック「エンド・テーマ」で使われた。
だが、ダリルはそれを知らなかった。この年、ダリルは大病をしてすべての仕事をキャンセル、大学教員も休職して治療に専念していて、連絡がつかなかったからだろう。
「シンプル・シングズ」は長らくイギリスのヒットチャートの上位に居座り続け、年間チャートにも君臨するほどの大ヒットになった。これはCDがとても売れていた時代の話だ。
のちにダリルは言った。
「あのアルバムのヒットのおかげで生活ができた」
そしてアルバムがチャートから姿を消した頃、ダリルは元気になって戻ってきた。今はエネルギッシュな70代だ。
行ったり来たりで恐縮だが、話をエドウィンに戻す。エドウィンのオーケストラ作品の特徴を一言で言うなら「よく鳴る」だ。
「よく鳴る」を簡単にいうと、舞台上にいる演奏者の数以上に、楽器群から大きな音量や多彩な音色の響きを引き出すオーケストレーションが施されている、ということになるだろうか。
反対に「あまり鳴らない」オーケストラ曲を書く作曲家(特に若い学生など)の作品は、ステージ上で、仮に80人近い演奏家が忙しく演奏していても、音が舞台から客席に効果的に届かず、音色がうまく響く瞬間が少ないのだ。
ここで少しオーケストレーションの話をしたい。
唐突だが、日本の遠足のおやつの計算は、僕が小学生の頃は「1人合計200円以内」が決まりだった。200円の菓子1個だけの子もいれば、僕みたいに10円の菓子(当時は多かった)を組み合わせて袋をパンパンにして持参する子もいる。僕は必ず先生に200円を超過していないか調べられた。
オーケストレーションはそれに似ている。
例えば2管編成(基本、フルート2本、オーボエ2本、クラリネット2本、ファゴット2本など、すべての木管楽器が2本ずつの編成)のオーケストラ曲を書くとする。この時、同じメロディを、例えば同時にフルート2本で吹かせると、当然、フルートの音だけがするメロディが流れる。だが、これをフルート1本とオーボエ1本で同時に同じメロディを吹かせたなら、フルートとオーボエの混合した、1つの楽器ではあり得ない音色が、そのメロディを響かせることになる。
さて、では、これをメロディが半分進んだあたりで、フルートとオーボエのダブりから、フルートとクラリネットにしたとしよう。そうすると、そのメロディの後半から少し音色が変化するが、フルートは引き続き吹いているわけで、同じ要素はありながらも音色は変化し、知らぬ間にそれまでオーボエだった音色の要素がクラリネットに変わる。
その変化をすごい速さで、例えば2音ごとに楽器のコンビネーションを変えて吹かせたりすると、万華鏡のように音の色彩が移ろうのだ。
今の話は単なる1つのメロディでの話で、オーケストラ作品には、いくつものメロディが途切れずに連続するし、メロディ以外にもいろんな音楽の要素が同時に鳴る。それを対旋律、ハーモニー、リズムと、すべての局面でオーケストレーションを進めると、あらゆる楽器による無数の組み合わせの音がミックスされた音響が、繚乱(りょうらん)することになる。
少ない数の楽器から多彩な音の花を咲かせるのが、オーケストレーションの醍醐味だと僕は思う。
エドウィンは、たいそうそれがうまい。かつてオーケストラでオーボエを吹いていたし、指揮もしているからだろう、まさに「よく鳴る」オーケストラ曲を書く作曲家なのだ。
断っておくが、指揮者でもある作曲家だからといって、オーケストレーションがうまいとは限らない。指揮者で、作曲もしてしまっているらしい某氏は、あれだけ世界の有名オーケストラの前に毎日立っているのに、彼が作曲した作品はというと、どうしてああいうオーケストレーションになってしまうのか不思議だ。そういう人はけっこう多い。
そんなわけで、大学院入学にあたって、4年間ダリルから学んだのとはまったく方向が違う音楽をエドウィンから学べる、と思うと僕の心は躍った。
だが、唯一の不満は、エドウィンも、僕の音楽に対して全然、批判的ではなかったことだった。
どんな作品を持っていっても、大変興奮して、僕の楽譜を見てくれた。だが、良きことしか言ってくれなかった。
1度、別の同門下生がエドウィンの授業を受けているのを、僕は短い時間だが見学した。彼のレッスンが延びて僕の時間に食い込み、「ちょっと部屋の隅で待ってて」と言われたのだ。彼は僕の親友だった。エドウィンは彼の作品に対して、かなり多くの批判的、否定的な指摘をしていたので、びっくりした。僕は複雑な思いがした。
僕の書くすべての音符に、正鵠(せいこく)を射(い)るような意見を言ってくれる先生ジョージ・ベンジャミン(1960年生まれのイギリスの作曲家、指揮者、ピアニストで、オリヴィエ・メシアンの弟子)に出会うのは、この2年間の修士課程を修了したあとだ。たった1音についての3時間に及ぶ授業、そしてその後、家に帰ってからも「やはりあの音はおかしいと思う」と携帯にメールが届くくらい、細かかったジョージ。その話はまたあとで。
それにしても、今これを書きながらしみじみ思うのは、自分は本当に先生に恵まれたということだ。人間的にも、作曲家としても、先生のタイプとしても、僕の人生が必要とした時に、必要な師が運命的に現れる。これは奇跡だった。
にもかかわらず、この王立音楽大学での大学院生活の2年間は、楽しかった記憶がほとんどない。練習棟に毎日入り浸りだったトリニティ音楽大学ほど、王立音楽大学には通わなかった。必要最小限、行っただけだった。
理由はこの2年間、すでに書いたように、同棲中のミレナのイギリス滞在のヴィザが切れる寸前に、急遽結婚した上、恒常的に生活費がなくて、音楽と関係ないところでの苦労が絶えなかったからだと思う。こんなかんじの生活は30歳になるまで続く。まったく冴えなかった。これは当時の愚痴だが、世界最高峰の音楽祭や指揮者から作曲依頼が来ているのに、ちっとも生活が楽にならないなんて、僕は、シューベルトや石川啄木の時代の人間かよ、豊かな現代に、こんな変な職業、他にあるのか、とよく思った。
王立音楽大学の学費は2年間支払わずに済んだが、物価の高いロンドンでミレナと2人して住むには、それなりにお金が必要だ。
この頃、大変物騒なエリア、ボウに住んでいた。大家さんはインド人のおばあさんで、悪い人ではないのだが、プロによるちゃんとした修理が必要なレベルの家のトラブルでも、すべて自分で直そうとする人だった。しかも修繕は適当で、不十分だった。要するに、ケチな締まり屋なのだ、2駅先の大家さん自身の家は、かなりの豪邸であるにもかかわらず。
僕らの家は台所の排水に問題があった。始終、温泉の硫黄臭(いおうしゅう)がする、と言ったらまだ聞こえがいいが、時に、耐えがたい悪臭に発展した。
ベッドルームとリヴィングルームがあるだけのアパート。リヴィングに台所が付いているタイプだ。屋根裏みたいなところを改造して、無理やり作った部屋なので、排水の問題も生じるんだろう。シャワーも、押し入れに、ただシャワーユニットを無理やりぎゅっと詰め込んだかんじだった。そして、すべてが汚ない。元来きれい好きで、細部にまで目が届くミレナは、相当つらい思いをしてそこに住んでいた。ある日、ミレナが、「もう無理。ここには住めない!」と宣言した。その時まで、僕らはそこに住んだ。5年間ほどだった。
思い出した。問題は玄関にもあった。僕らのアパート自体は細長い3階建てで、ロンドンによくある、ジョージアンハウスと呼ばれる18~19世紀初頭の、ジョージ王時代の建築様式の家だった。大家さんは、昔は1軒だったものを内部でいくつかの別のアパートに小分けして、それぞれ売ったり、貸し出したりするのだ。この家は2つに分けられていた。1階にメインの玄関(昔この家が1つの家だった時のもの)があって、これは問題なかった。
僕らのは屋根裏を改造したアパートなので、最上階だ。その下は、1階と2階とで1世帯で、日頃、スペインに住んでいる大家さんの息子(といっても、かなりのおっさん)がロンドンに帰ってきた時だけ、そこに住んだ。帰郷時はいつも、スペイン人の彼氏と2人して滞在した。2人ともナイスな人たちなので、そこも全然、問題なかった。

問題は、僕らの屋根裏部屋の玄関だった。専用の特製ドアが別にあった。特製とはいっても、実際には大家さんが取り付けた、単なるベニヤ板1枚だ。僕の背丈よりちょっと高いベニヤ板の上には天井の空間がある。2階からさらに階段を上ったところにある、屋根裏の物置をアパートに改造するために、気持ち程度のドアだけを無理やりそこに取り付けたのだ。公衆トイレの個室のドアみたい、といえばわかってもらえるだろうか。そのドアを閉めたところで天井まで空間は丸空きだ。
1年の9割以上、息子はスペインにいるので、この3階建ての建物にいるのは、たいがい僕と妻だけだ。だから、ベニヤ板のドアに付いたチャチな金属のフックが僕らのアパートの鍵だ、と言われても、許容範囲といえば、いえるのかもしれない。僕には、特に住む場所への気取りもこだわりもない。最低限が保障されていれば、ある意味どんなところだっていい。でも、ここは極限に近かった。
リヴィングにある台所と反対側の壁に、備え付けの飾り棚(おそらく大家さんのお手製)があった。その棚を机がわりにして僕は作曲をした。机を置くスペースが他にないのだ。五線紙に集中すると棚が壁から外れ、棚の上部の中身が頭に落ちてきて、しばしば往生した。家のインテリアのすべての造作(ぞうさく)が適当で、生活するにはギリギリ感満載のアパートだった。
なぜ、わざわざそんなところに住むのだ? と思うかもしれないが、とにかく家賃が安かったから、としかいいようがない。相場の半額以下、いや3分の1くらいで、ひと月650ポンド(光熱費込み)ほどだったろうか。
2021年で44歳になったが、そういえば、いまだに自分が住みたいと思うタイプのアパートに住めたことがない。おそらく一生、そんな経験はできない気がする。
この大家さんは「学生以外は住まわせられない」とよく言っていた。おそらく税制上なんらかの優遇措置があったのだろう。それとも、学生ならここでも我慢する、と思っていたのだろうか。
大家さんは、自分の店子(たなこ)(僕)が王立音楽大学大学院に入ったことをとても喜んでいた。こういう時に世界的有名大学は助かる。彼女はクラシック音楽に詳しく、わざわざ僕のコンサートに足を運んでくれたりもした。僕がここから転居した後も、「こんな手紙が来ていたよ」とよく転送してくれた。イギリスでは元の大家さんが転居先に転送してくれるなんてことはまずない。
ある時、彼女から1通の手紙が転送された。送り主の名前は、虫眼鏡じゃないと読めないような小さな字だった。ピエール・ブーレーズからだった。それを彼女に伝えたら「へーっ、あのブーレーズからの手紙だったんだね。いいことした!」と喜んでくれた。ブーレーズのことも知っている人だった。よくぞ転送してくれたものだ。
この時期、僕は5歳くらいの子供たちにアルバイトでピアノを教えていた。週に7人くらいだったろうか。それぞれの家に通った。
僕が住んでいたのはロンドン東部だが、王立音楽大学は、最高級住宅エリアのサウス・ケンジントンにある。映画で有名になったノッティング・ヒルが近いし、高級住宅地の代名詞チェルシーにも近い。王室御用達百貨店ハロッズがある、ナイツブリッジも歩いてすぐだ。
ピアノを教えていた子供たちはみな、この界隈の住人で、全員が豪邸に住んでいた。アメリカ、中東、フランスの家庭の子弟だった。イギリス人はいなかった。
ある日、アメリカ人の男の子の家に行き、ドアのチャイムを鳴らすと、真っ青な顔をしてお母さんが出てきた。
「今、アメリカですごいことが起きた。あなたの国にも金融関係が集まる大きなビルってあるかしら? ニューヨークのそうしたビルに突然、飛行機が突っ込んで……」
まったく何を言ってるんだろうか、この人は。飛行機がビルに突っ込む? アクション映画でもあるまいし。僕は、そんなことより、まったく練習をしない、この家の5歳児のレッスンを早く終えて、家で作曲の続きをしたい、とその時、思った。
当然、すぐにわかるのだが、9・11のテロだった。当時、携帯電話は持っていたが、スマホではないので、インターネット・ニュースは地下鉄の中では読めなかった。僕が、ロンドン東部からこの高級住宅エリアまで地下鉄で1時間の移動中、マンハッタンで世界貿易センタービルが、ハイジャックされた旅客機によって襲撃され、崩壊したのだった。よりによってその直後、アメリカ人の男の子を教えることになるとは。
だが、僕はいつもどおりレッスンをした。彼は何度言っても、ピアノの真ん中のドをわかってくれない。
「『水泳とピアノ、どっち習いたい?』とお母さんに訊かれたから『水泳!』って言ったのに、僕は今、あんたの目の前に座ってるんだよね」
この生意気な5歳児は、この日もそう愚痴を言った。だが、たしかに同情の余地はある。どうして親は、無理やり音楽をやらせるのか。こういう親はたいてい音楽を知らない。知らないから習わせるのだ。
だが、ある日、この、とにかくピアノが好きになれない彼(名前が思い出せない)が、かなり小さなカラー液晶のニンテンドーのゲームボーイをポケットに忍ばせていたことから、事態は変わった。
「真ん中のドはどこだっけ?」
「ほら、これ(ゲームボーイ)……知ってる?」
ゲームボーイなんてどうでもいい、今は真ん中のドだよ。えっ、でも、これスーパーマリオだろ。知ってる? って君、何言ってるの。僕は日本人だよ。知ってるもなにもないよ。
彼はマリオをやり始めた。
「違うよ、そこ上に行ってワープだよ。えっ、ワープを知らない? なんで? 君、学校で友だちいないんじゃないの。誰でも知ってるよ、そんなの。ちょっと貸してみ。こう、上にあがると、ね、ワープできるんだよ」
ワープを教えた途端、彼の僕を見る目は変わり、ピアノにも乗り気になった。すぐさま真ん中のドどころか、次々と曲を練習し始め、マスターしていった。彼は今は26歳くらいだろうか。何をしているだろう。
他にも、レバノン人のシングルマザーの息子さんを教えたことがあった。お母さんは、息子が大人の男性に接する機会が少ないから、と僕の存在を喜んでくれたようだった。ただ困ったことに、レッスン後、お茶飲んで行け、とかディナーを食べていかないか、など、ことあるごとに誘われた。そこはプロフェッショナルの笑顔で断り、レッスンが終わるとすぐその家を出た。
こうして、子供たちにアルバイトでピアノを教える時間が、作曲の時間を侵食するのが僕は嫌だった。家賃のためのアルバイトであり、一刻も早く家に帰って曲作りの続きがしたかった。乱暴な言い方になるが、僕には、生活の金を稼ぐ仕事は、必要以上に作曲の時間を蝕む脅威の時間でもあった。
その考えは、今でもさほど変わらない。アメリカの大学から「教授をしないか」とか声をかけてもらうことがあるが、毎回断っている。僕は作曲がしたいのであって教師になりたいわけではない。
もちろん時々は教えたりするし、その時はベストを尽くす。少しの時間なら気分転換にもなる。現在、王立音楽大学の作曲科の教授として、生徒を1人だけ教えている。それも自宅で教えるだけだから、大学から「会議に顔を出してくれ」とも言われない。報告書の提出義務もない。大学側は、学生から僕の家での授業がどんなであるかを聞いて、それで彼がハッピーか確認しているはずだ。
僕は学生との最後のレッスンでは必ず、「教師にはなるべくならないで。ただ作曲してほしい。グッドラック」と言う。
先生になりたい人は、なればいい。だが、僕に教わりたいという学生のほとんどは、「音楽の未来を変えてやる!」と意気込む作曲家の卵ばかりだ。作曲家は金にならない。でも、簡素な生活をすることで出費を減らせば、作曲に関係のない「お金のための仕事」、例えば音楽大学の教授などしなくても済むのだ。
人間の欲望は人それぞれで、考え方もそれぞれだが、お金がたくさん必要な生活をしないと満足できない人は不幸だと、僕は思う。
とはいっても、この2000年当時、子供にピアノを教えるだけでは、どうしても生活費が足りないので、エドウィンに「何かないですか」と泣きついたらアルバイトを紹介してくれた。それが写譜だった。
ちょうど彼が、ベートーヴェンの弦楽四重奏曲「大フーガ(Grosse Fuge)」をウィンドオーケストラ(吹奏楽)用に編曲したところだった。その楽譜は、リコルディという音楽出版社から出版されるので、僕はエドウィンの手書きスコアを、パソコンに入力して清書し、パート譜も作った。その作業でアルバイト代をもらった。
これが、リコルディと僕の最初の接点だった。その時のリコルディのロンドン支社(現在はベルリン支社に吸収されて、ない)の女性ボスであるミランダが、僕に作曲家として出版契約をオファーしてくれるのは、この5年後の話だ。
この頃、僕は結婚し、妻ミレナは、きれいさっぱり音楽をやめて幼稚園・保育園(イギリスでは、この2つに違いはない)の先生になる資格を取る勉強をしながら、その見習いとして働き始めた。小さい子供たち相手に働いていると、必ず風邪を伝染(うつ)されて引きっぱなしになるそうだが、ミレナもそうだった。当時、よくもまあこんなに連続して病気で休む見習いに、給料が出るもんだな、と感心したものだ。
とはいっても、イギリスの幼稚園の先生の給料はひじょうに低い。見習いとなるともっと安い。実家暮らしか、夫(ないし妻)が会社勤めをしていないと、とてもじゃないが幼稚園の先生の給料だけで生活はできない。
僕は僕で、他に、20代前半の作曲家に回ってくる教育プログラムの作曲の仕事を頼まれてよくやった。
例えば、ロンドン郊外の高校のプロジェクトから、「キリストの死から復活までを、3分で描いた作品を書いてほしい」と注文された。さらにそれは「生徒の中にフルートのうまい子が1人いるので、フルートと生徒たちの合唱のコラボ作品で」とも言われた。これも現在、作品リストには入れていない。教育関係は、政府からの助成金が下りるので学校も委嘱しやすいのだ。
また、こんなこともあった。ギリシャ人の作曲家の親友が、ロンドン北部の小学校で音楽を教えていた。当時、ギリシャの男性は、1年間、兵役に就くことが法律で義務づけられていて、彼は帰国せねばならず、軍隊にいる間、僕に代用教員になってほしい、と言う。親友の頼みなので僕は受けた。
小学校に行ってみると、僕が受け持つのは音楽の授業ではなく、個々の子供にピアノの個人レッスンをすることだった。行くたび次から次へとやって来る子供たちにピアノを教えた。彼らとはうまくつきあえたと思うが、僕にとってはこれも無駄な時間にしか感じられず苦痛だった。
始まってすぐに、これは1学期ならいいけど、1年は続けられないな、と思った。親友は親友で、「軍隊に1年もいられない。早くロンドンに帰ってきて作曲の勉強を続けたい」と言った。そりゃそうだ、僕らは作曲家なんだから。
彼はゲイだった。そこで彼は、試みに軍の教官に相談した。
「同じ軍隊の若い男性たちと一緒にシャワーを浴びたり、すべてを共にする集団生活が耐えられません。なぜかというと、自分が他の若く美しい男性に何かしてしまうかもしれないから。ノイローゼになりそうなんです」
もちろん彼は話を誇張したわけだが、教官はそれを真摯に受け止め、軍の安全を考え、彼を即刻、軍隊から除名する手続きをした。
そんなわけで、親友は予定よりずいぶん早くロンドンに戻ってきた。僕も小学校の仕事をたちまち彼に返すことができた。現在、彼はイギリス人男性と結婚して、僕の家の近所に住んでいる。僕たちとは家族ぐるみのつきあいだ。すべてにおいてうまくいった。
結局のところ、僕の2年間の大学院時代がどうも冴えないのは、今、冷静に考えると、じつは作曲のほうがスランプだったからだ。
この頃、短期間だが、僕は日本の伝統音楽に強く興味を持ち、勉強し始めていた。テンポの遅い瞑想的な作品を書いたり、日本の伝統音楽、例えば尺八の音楽みたいなフルート曲を書いたりした。半年間くらいだったろうか。
僕には、音楽的にあまり良くないアイデアやモチーフで曲を作っても、いざ出来上がってリハーサルすると、演奏が崩壊状態になるようなことがない。わりにいつも「まあまあな響き」にはなる。だが、そこが落とし穴なのだ。つまり、音楽的な欠陥や失敗に気づきにくい。無難な音楽ほど最悪なものはないじゃないか。
もっと、音楽的に不器用不細工な作品なら、リハーサルは崩壊状態になる。崩壊状態とは、奏者が揃って演奏できず、とにかく音楽が先に進まず、止まるのだ。その場にいる指揮者や奏者、そして作曲家本人にも、目の前の音楽が「嗚呼(ああ)これは失敗だ」と露骨にわかる。だが、僕の場合はそうはならないから、逆に自分の書く音楽にいつも神経を尖らせて判断せねばならない。
この頃、僕は、自分のキャラクターに完全に反する音楽を目指して、空回りしていた。思えばそれまで、いろいろなコンクールで優勝したり入選したりしていたのに、そんなことがガタッと減った時期だった。もちろんコンクールに選ばれるのがいい曲、というわけではない。だが、誰も僕には言わなかったが、僕の作品のクオリティが下がっていた時期だったと思う。壁なき壁を動かそうともがいていた。
でも半年で、これは徒労だとわかった。
自分では気づかないが、僕は早口でしゃべるらしいし、エネルギッシュらしいし、僕といっしょにいるとエネルギーが吸い取られそうになるらしいし、鬱陶しいし、他人を疲れさせるらしい。物心ついて以来、ずっと、そう言われ続けた。
そんな人間が、瞑想的な音楽を目指して、いいことがあるはずがないじゃないか。だいぶ遠回り、というか無駄な時間を過ごしてしまった。瞑想じゃなくて迷走だ。
だいたい、日本人が、日本古来の音楽の響きを踏襲して作曲するなんて、なんと退屈なことよ、と思い始めた。当たり前すぎる。
日本人として生まれたことは、拭(ぬぐ)いがたいアイデンティティではあるだろうが、これは単なる偶然であって、別に僕の努力の賜物(たまもの)でもなんでもない。親の都合でなっただけだ。自分の意思でなく、たまたま生まれた国を勝手に誇りに思い、それにしがみつくといった感性や行為はバカバカしい、と感じ始めた。
それである日、この時期に書いた作品(たくさんあった)をすべて破棄した。自分の外側にあるものを使うのでなく、やはり自分の内側から湧き出す新しい音楽を書こうと思った。
すると腰のベルトのデカい携帯電話(当時はそうだった)が鳴った。ジリアン・ムーアからだった。彼女は室内オーケストラ、ロンドン・シンフォニエッタの音楽監督だ。話をするのは2000年のロンドン・シンフォニエッタによる僕の「フローズン・ヒート」初演以来。1年くらい経っていた。
「5人のアンサンブルとライヴ・エレクトロニクスの曲を書く気はある? 指揮者はマーティン・ブラビンズ。演奏はもちろんロンドン・シンフォニエッタ」
もはやスランプは脱していた。ライヴ・エレクトロニクス(その場で演奏された音をリアルタイムで機械的に変調して鳴らすこと)の音楽は、書いたことがなかったので是が非でもやりたかった。コンサートはたしか4カ月後だったと思う。作品タイトルは「ブルー・スカイ・フォーリング(Blue Sky Falling =落下する青空)」に決めた。
本番前日の、最初で最後のリハーサルで指揮者ブラビンズと会った。初めてだった。
イギリスでは「世界初演といえばブラビンズ」というくらい、夥(おびただ)しい数の現代音楽を彼は振っていた。その理由はじつに納得のいくものだ。
イギリスの音楽界では、どんな複雑な作品でも、リハーサルにあまり時間を取らない。1回ないし多くて2回だ。そんな条件下の本番で、例えばエレクトロニクス(コンピュータ)がうまく作動しないなどシリアスでシビアなトラブルが起きても、彼は、慌てることなく本番を進められる。僕の作品の世界初演にたびたび関わってくれる、ある友人プレイヤーは、指揮がブラビンズでない場合、「ああ、マーティンだったらどんなにか安心だろうに」とよく口にする。
これ以来、ブラビンズはたびたび僕の曲を振ってくれる。もう長いつきあいだ。こんなこともあった。
2011年のコントラバス協奏曲の世界初演時、僕の娘はまだ赤ん坊だった。妻が、どうしてもこの作品の世界初演を聴きたいと言う。演奏はブラビンズ指揮のロンドン・シンフォニエッタ(ソリストはエンノ・ゼンフト)。
それをマーティンに相談すると、彼は「簡単じゃないか。僕が、本番で振っている間、僕の楽屋を、赤ちゃんとベビーシッターをしてくれる友人とで使えばいいさ。僕は楽屋、使えないんだし」と笑いながら言ってくれた。ヨーロッパでは、作曲家に楽屋を用意してくれるコンサートは、ほとんどない。通常、指揮者という人種は楽屋というものに関して、狭いとか、広すぎるとか、居心地が悪いとか、誰々の隣は嫌だとか、かなり細かくて神経質な不満を宣(のたま)うが、彼は、ひたすらシンプルかつ大らかなのだ。
そういうすべてを総合して、コンサートのプロデューサーであるオーケストラのジェネラルマネージャーが、複雑な現代音楽をプログラムに入れる時に、ブラビンズに指揮を依頼するのは、とても理に適っている。
こうして、将来、プロの作曲家として後々まで深く関わる人たちと最初に仕事をしだしたのがこの時期だった。
(お知らせ)
2022年3月16日19時半〜、新刊や作曲の裏話がたっぷり聞ける藤倉大さんオンライン対談を開催します。詳しくは幻冬舎大学のページをご覧ください。